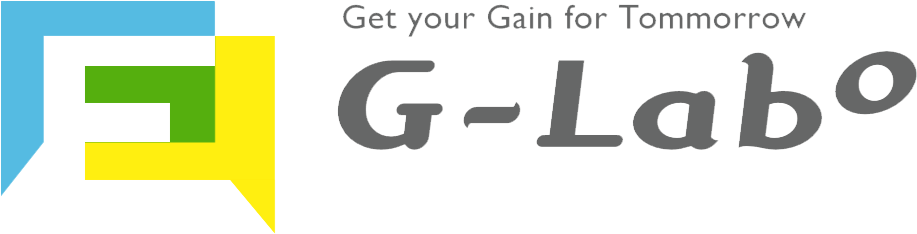昼間がとても暑くなってきたので、スポーツジムと契約することにしました。
昼間にジョギングをすると結構しんどいことが判明したんですよね。
ちょこっとジョギングを初めてから3年くらい経ちますが、今までは出社前に走ってました。
会社勤めの身だったので朝から夕方までは拘束されますし、夜は夜で色んな予定が入る可能性が高かったので避けてました。
それが自由な身になると自分の都合で動くので、朝は弱いので避ける。
夜は研修なども入ることがあるので避ける。
ということで昼間に走ってましたが、暑くてダメですね。
7月からは初めてのスポーツジムを試してみようかと思います!
前回は新しい視点を持つために、長期経営計画は役に立ちますという話をしました。
今まで見ていた数字、予測している数字とは異なる観点で作成をするため、強制的に思考を切り替える必要が出てくるんです。
しばらくは切り替えられずに思考停止をする時もありますが、これも回数をこなすことで解決することがあります。
何事も、最初からうまくいくことはほぼありません。
そして今回は銀行と話す際に、強力な武器になりますというお話です。
経営を行う上で、切っても切り離せないのが資金の調達です。
会社を設立した時点では株主がその役割を担いますが、会社を大きくしていく上で重要になってくるのが金融機関でしょう。
金融機関は資金の調達をする上で重要な役割を担うことがほとんどです。

金融機関はいわゆる金貸し業です。
お金を必要としている人にお金を貸して、その利息で利益をあげるビジネスなんですよね。
わたしは結構な大人になるまで、銀行は特別な存在で何らかの力を持っていると思っていました。
一般人が近寄るのは畏れ多いような感覚で、不用意に使ってはいけないなんていう雰囲気があったのを覚えています。
日本人って金融リテラシーがあまりないと言われていますが、お金に関する教育って学校はしないですし、家庭内でもタブー視されていることが多いのではないでしょうか。
お金の話をするなんてはしたない、的な雰囲気ってありますよね。
一般常識として借金は悪、貯金があることが将来の安心、みたいな感覚が広まっているように思えます。
なので、日本人って投資に弱かったり、タンス預金が増えたりと言われている。
でも、実は日本でも江戸時代は今よりも金融リテラシーが高かったと言われています。
それは太閤検地によって田畑の面積が定められ、自分たちがどの程度の収入があるのかを自分で計算ができるようになったこと。
そして、自分の収入は自分で工夫をして上げられるし、採れた米をどうするかの選択権があったからです。
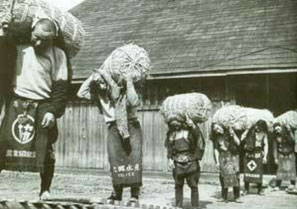
多くの家が個人事業主のような働き方をしている場合がほとんどで、必要に迫られて和算という文化が育まれました。
利息の計算をするのに必要な複利計算をするために、数列の学問があったほどです。
家を存続させるため、家族を養うために必要な知識を得る。
その知識が和算であり、お金に正面から向き合う姿勢でした。
それが太平洋戦争後、会社に雇われて働く人の割合が急激に増えました。
そうすると毎月一定の給料が支払われるようになり、一般市民の生活はとても安定します。
戦後は作れば何でも売れる時代。
目の前の仕事を一生懸命こなせば十分な働きになります。
毎月の給料と退職金でお金の心配がなくなり、お金に関しての知識はいらなくなったも同然ですよね。
個人は金融から解放された形になりました。
銀行とのお付き合いは家を買う時くらいになったと言ってもいいくらい。
なので、銀行はどんな仕事をしているかもよくわからないし、金融に関しても疎くなったのかもしれません。
というわけで、本来書こうと思っていたことから大幅に逸れましたが、今日はここまで~。
続きは明日。